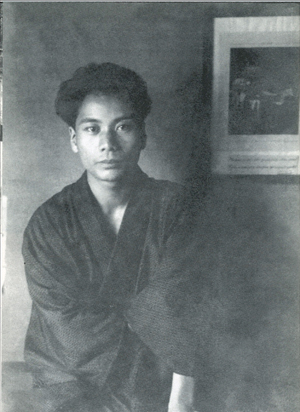
上野壮夫の詩に対する考えを知る上で大事な言葉がある。第一詩集『黒の時代』の「あとがき」に、次の一文がある。
「詩をもふくめて『文学』というものには、絵画や音楽におけるような『美的完成度』などはそれほど重要でないのではないか、ということである。首尾一貫して定石どおり美しくまとまった作品よりも、むしろ荒々しく生命力に溢れた未完成の作品のほうが、多くの場合感動が深いことは事実であり、いわゆる技巧的な作品に比して後者の方が、たとえば、『生きる』ことと『表現』することとが同じ重さで行間に詰まっていて、その結果、別の意味での質の高さと美的感動を生むのではないか、と考えるようになったのだ」
ということで、前に創作した「長篇詩『黒の時代』を、未完成ではあるがあえて復刻する気になったのも、そういう考え方からである」と唱えている。まったく同感である。
詩にかぎらず文学作品では、荒削りで感情表現を露わにしたほうが心に突き刺さり共鳴力を強く持っていることが多い。作家が歳を経て技巧的に走り、修練された作品には何かもの足りなさを感じてしまうことが多々あるのは事実だ。
『黒の時代』こそ、ファシズム下で沈黙を強いられた詩人の呻きがあり、窒息しそうな社会でもがいて生きる生身の人間の姿が浮かび、心がなぜか吸い寄せられていく。
エピソードを一つ。
ある日のこと、上野家に客人が集まっていた。1台の蓄音機がメロディーを奏でている。ハワイ帰りの新進作家、中島直人が多喜子を誘って踊り出した。突然、隣の部屋にいた壮夫が多喜子の襟首をつかんで投げ飛ばす。多喜子は隣の部屋に倒れ、襖には大きな穴があいた。「人の奥さんとは踊ってはいけないよ」と文士仲間が中島直人を諭した。
皆が帰ってから壮夫は多喜子に漏らした。「運動が壊滅状態になって虚脱状態だったんだ。自分の行く道さえつかめなかった。そんな時、おまえがちゃらちゃらした洋行帰りのブルジョア作家と何の屈託もなく踊っている。思わずかっとなってね」
雑誌『人民文庫』に寄り添った2人にも時代の重たさはどうしょうもなかった。
|

