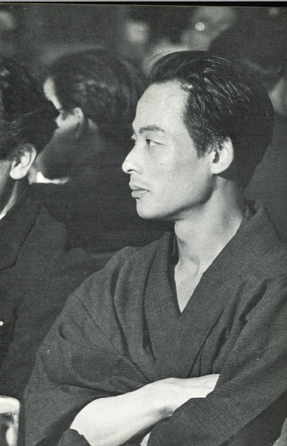 古澤元の一本気な性格を示す文章がある。息子の古澤襄がまとめた本『沢内農民の興亡――古澤元とその文学』(1998年、朝日書林)の中に、未発表エッセイが掲載されている。「偶感追想」(1937年)の一文である。 古澤元の一本気な性格を示す文章がある。息子の古澤襄がまとめた本『沢内農民の興亡――古澤元とその文学』(1998年、朝日書林)の中に、未発表エッセイが掲載されている。「偶感追想」(1937年)の一文である。
『戦旗』に初めて書いた「高知の漁民騒動」を作家の中野重治に見てもらう。すると書き込みばかりされて「この文章は駄目じゃないか」と厳しい助言を受けた。だがそのまま掲載してしまう。そして一言がふるっている。
「意地張りなほうなので、どうせ、運動中は小説など書けはしない、さればと言って運動から足を抜く卑怯な真似も嫌だったので、行くところまで行け、行って牢にでも入り、出て来たら、その時から小説を書こうという半ば自棄な考えに考えを固めてしまった。それ以来、自分は実に典型的な文化運動者、編輯員として『戦旗』が潰れる直前まで誰からも非難を受けぬ真面目さで活動し通した」
はっきりと言う、古澤の面目躍如の一コマである。
古澤は独特の勘を持っているそれは大衆性からきたものだろう。プロレタリア文学運動の欠陥を鋭く指摘し、批判した文章は今日にも生きていて考えさせられることが多い。『人民文庫』創刊号に書いた「雑言一束」がある。
「ところでまた、現在に極めて近い過去に材をとった小説でも、もし伏字ずくめの小説となると、興味どころか、多くの場合甚だ腹が立ってくる。ことに、その小説家がマルキシズムを一通り学び、プロレタリア文学運動の渦の中にきたえられてきた経歴があったりすると、ますます嫌になる。
苦労に苦労し抜いた筈の伏字ご難について、さらに工夫も配慮もせず相変わらず伏字覚悟の小説を書いているのを見ると、この小説家はよほど間が抜けているか、でなければ随分図々しく構えているものだと思う」
何が言いたいかというと、国家権力の圧力による伏せ字だとしても、判読できないような伏せ字小説を発表するような作家は、作家としての努力と苦労をしていない怠け者だと指弾しているのだ。
確かに権力側の規制で表現の自由が奪われているにしても、読者に創意工夫した文章力で伝えるのが技量ではないかと問う。一理がある。古澤元、戦後を生きていたらどんな小説作品を遺しただろうか、惜しまれる存在の人である。
|

