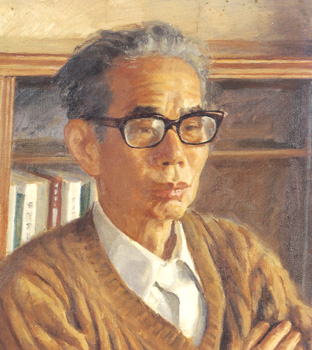 『わが小説修業』(昭和14年10月発行、月刊文章編輯部)に、澁川驍(ぎょう)は、「将棋に喩へて」を書いている。小説一筋の心根がよく現れている。 『わが小説修業』(昭和14年10月発行、月刊文章編輯部)に、澁川驍(ぎょう)は、「将棋に喩へて」を書いている。小説一筋の心根がよく現れている。
「将棋をするたびに、私はいつも感ずる。相手に勝とう勝とうと思っていると、かえって形勢が悪くなって、負けることが多い。そういう勝負を度外視して、静かな気持ちで対していると馬鹿に調子がよくなって行く」
その自負心の強さが出過ぎるとよい結果は出ないと言う。芸術の世界にも同じことが通じると言及する。
「私はこれは芸術の世界でも同じことだと常に思う。勝とう勝とうとする気持ちは、相手の敵一人を目当てに、策戦を練っているわけである。従って、幾分でも相手の技よりも立ち勝っていることが確かめられゝば、すぐ駒を持つ手が動き勝なのである。しかし、その計算には、僅かな優越しか予期されていないから、ちょっとした誤算のためにも忽ち、陣営は一たまりもなく掻き乱されてしまうのだ。小説においても、制作の目標が仲間の好評だとか、月月の文芸時評などの標準などである場合には、とかく充分の力は発揮できず、自分の予期していた力すら振い出すことができないのだ」
その上で、小説を描くのに一番大事なことは「何よりも考えることだ」と言う。小説では、正確な表現が密度を加えていくと核心に触れる。だから、「作家が原稿紙に向って筆を取った時、すでに八分通り出来上っているものだといっても、あまり過言ではないと思う」と語る。
どういう意味かといえば、しっかりと考えを練り磨かないかぎりは高い文学の表現は原稿紙上に現れてこないと言い切っている。長いこと厳格に文学と対峙してきた作家の姿勢をみることができる。
この作家の特質を見ることができる逸話がある。父と母の想い出に触れた息子の述懐にふと目を奪われる。
「父の晩年における母との共同作業が、『青桐書房』の経営である。父の著作物を製作するための出版社である。自分の書いた文章を、自分の理想とする形態で出版するという、おそらく物書きにとっては最高のぜい沢と思われることをやったと、私は思う」
作家冥利に尽きる幸せな人生を過ごした。
|

