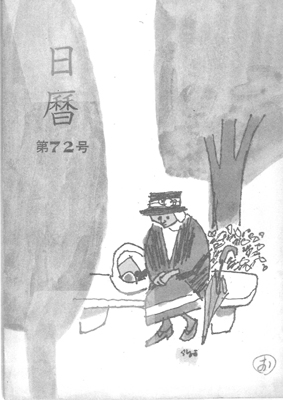 石光葆(いしみつしげる)は、1907(明治40)年3月1日、広島市に生まれた。東京帝国大学国文科を卒業後、博文館、中央公論社、朝日新聞社で仕事をしながら小説を書いた。 石光葆(いしみつしげる)は、1907(明治40)年3月1日、広島市に生まれた。東京帝国大学国文科を卒業後、博文館、中央公論社、朝日新聞社で仕事をしながら小説を書いた。
雑誌『集団』『日暦』や『人民文庫』に関わり小説を発表する文学関係では、「宇野浩二を囲む会」や作家の高見順とは40年近くの交流があったという。 作品には、『明暗の境』『若い夢』『女愁』などがある。1988(昭和63)年3月6日に81歳で死去した。
作家には独立独歩の人が多いが、石光葆は交友関係を大事にしていたことが残されている記録からわかる。
『日歴』第72号には「編集後期を兼ねて」で
石光葆が相次ぐ同人の死を悼んでいる |
戦後復刊した『日暦』の編集をしていたが、72号(昭和53年5月発行)に「編集後記を兼ねて」をまとめている。次々と亡くなっていく作家仲間への哀悼には、心の痛みがよく現れている。
「第70号の藤田貞次につづいて、またもや追悼号となった。しかも今度は摩寿意義郎と大谷藤子の二人。71号の『編集後記』に「摩寿意義郎が亡くなったので、次号も追悼号……となると気が重くなる。と書いたが」とある。同時代を共に歩んだ仲間たちが消えていくことにやるせない気持ちでたまらなかったのだろう。
石光葆は、文学することが心底好きだったと思う。
『人民文庫』創刊号に書いた「二重生活」にそれがよく現れている。「勤め人生活」を第二義的に考えていると言い放っている。
「私たちが文学をやるのは経済的な理由からではなく、ましてや道楽でもない。世が世智辛くなり生き難くなればなるほど、文学への欲求が高まる」という。
勤め人と作家の生活、昼はぐったりとして元気のない身体も、夜の自分の生活に戻ると不思議に生き生きとしてくる。夜が深まるにつれて、眼も頭も冴えわたってしょうがないという石光葆は、小説を創作するのが好きで好きで仕方なかったのだろう。
そこには己の姿と向き合い、心おきなく言いたいことと考えを自由に表現できることへの悦びがあふれているとしか思えない。作家冥利に尽きる人生だ。 |

