|
|
|
| 2011年1月11日 |
|
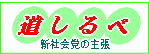 |
|
|
|
| 新防衛大綱 |
|
|
| 危険で不毛な対中軍拡路線 |
|
|
|
|
|
|
菅内閣は12月17日、今後10年間を見通した「新防衛大綱」と5年間の「中期防」を閣議決定した。長年「専守防衛」の証明とされた「基盤的防衛力構想」を廃棄し、中国対象の「動的防衛力」への大転換とグローバル「日米同盟」をめざす危険な代物だ。
民主党政権下で初の新防衛大綱は、右往左往の「政治主導」と対米腰砕け、相当数の国家主義勢力などから、どれほどひどい大綱になるか懸念されたが、果して昨年8月の、外務・防衛省主導の新安保防衛懇報告の方向、概念をほぼそのまま、なぞったものだった。
危険な「動的抑止力」
新大綱は、国際的にも日本に対しても大規模戦争の可能性は低いが、地域的な民族・宗教紛争や、領土・主権経済権益などで武力紛争には至らない「グレーゾーンの紛争」は増加とし、宇宙やサイバー空間を含む「各種事態にシームレス(継ぎ目なし)に対応」との方向を打ち出した。
いかなる紛争や問題も独自の背景や条件を持っており、それを一般的に「軍事力の役割の多様化と重要性」に結びつける論法は欺瞞的だ。また、あらゆる事態へのシームレスな対応とは、軍事力の無制限の増大になりうる。
その上で新大綱は、「従来の基盤的防衛力構想」を否定し、「即応性、機動性、柔軟性、持続性、多目的性を備えた『動的防衛力』」を打ち出した。新安保防衛懇は、34年間「専守防衛」の証とされてきた基盤的防衛力構想の放棄と「動的抑止力」概念を提起したが、憲法が禁じる「武力による威嚇」になりうるとの批判を受け、大綱では言い換えた(本文にはまだ「動的な抑止力を重視」とある)。
また、グローバル安保の取組みで「NGOとの連携」、「PKO5原則の見直し」も盛り込まれたが、NGOの中立性や信頼を崩す軍民合同作戦や、PKOでの武力行使拡大への道を開くものだ。
武器禁輸緩和問題は「対応方策を検討」という曖昧な表現にとどまったが、国会運営上の社民党との妥協の産物で、撤回ではない。
対中軍事態勢を増強
新大綱は、「自衛隊配備の空白地域の島嶼防衛」を異常に強調。だが実体は、中国海空軍への対抗が主目的。琉球列島中心に陸海空自衛隊を増強し「南西の壁」を築く戦略だ。
新中期防では、与那国島に陸自監視部隊の配備検討、初動部隊を新編成し沖縄配備、潜水艦を増強、護衛艦部隊を機動運用化、那覇基地の戦闘機部隊を2個に増強、早期警戒機を常時運用、F4後継機を配備、対潜哨戒機を延命、巡航ミサイル対処、地対艦ミサイル配備、MD部隊の沖縄配備とイージス艦6隻体制、新型輸送機配備、通信衛星を含む指揮統制強化、サイバー攻撃対処組織の新設など、目一杯に並ぶ(予算膨張で、戦車と火砲を3分の1縮減するが、陸自定員は千人減のみ)。
中国は直ちに「不快感」を表明したが、これだけの武力を突き付けておいて「戦略的パートナー」も「東アジア共同体」もあったものではない。「安全保障」で最も重要な「平和の枠組み作り」の提起も発想もなく、憲法9条の実体的突破を進める動きを止めよう。
|
|
|
|
|
|

