|
|
|
| 2011年1月18日 |
|
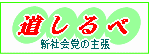 |
|
|
|
| 2011年春闘 |
|
|
| 個別交渉から統一闘争へ |
|
|
|
|
|
|
1997年をピークに個人所得は下降線をたどっており、「大幅賃上げ要求で、不満なときはストライキ」のかけ声もトーンダウンしている。11春闘を反撃の春闘にするには、個別交渉の〝打破〟が求められる。スケジュール闘争では賃上げはできない。
年が明け、ナショナルセンター、産別の春闘方針が決定した。
「速やかにピーク時(97年)の水準まで復元する」(連合)、「全ての労働者の賃上げによる景気回復で雇用を守れ」(全労連)、「働きがいのある人間らしい仕事の実現」(全労協)をスローガンに掲げ11春闘が本格的にスタートした。
企業は太る一方だが
この1年、大企業の収益は伸び続けた。半面、労働者の賃金は抑えられ、非正規雇用などが切り捨てられる状況にある。
日本企業の内部留保は240兆円を超えている。「国際競争力」を名目にした法人税減税は、内部留保をさらに膨らませることになる。菅直人首相が「減税分を賃上げと雇用に回してほしい」と申し入れても馬耳東風だ。
経団連は1990年代まで、「春が来なければよい」と春闘を嫌がっていたが、2000年代に入って逆転した。交渉方式が産別交渉から個別交渉にすり替えられ、労働者全員が参加する春闘が分散させられたからだ。
「不満なときはストライキ」と、全盛期の春闘は産別闘争がリードしていた。今は、ナショナルセンター、産別の高らかなかけ声があっても、闘う部隊は単組(個別交渉)に移行させられている。横断的な労働組合の団結が組めないなか、経営側に軍配が上がり続けているのだ。
国内消費の60%は個人消費だ。個人消費が増えないことには、景気回復・経済成長はない。経営側は1990年代からのグローバル化で、「国際競争に勝て」と労働者の尻をムチ打って膨大な内部留保を築いてきた。
それが、労働者に分配されることはない。経営者は、賃上げ抑制と非正規雇用を見直そうともしない。その結果、日本の個人所得順位は世界第2位から18位まで下降している。
連合は、「賃金カーブと個別賃金水準の維持を図り、定期昇給のない組合は社会的水準である5000円の賃上げを図る」というが、具体的賃金交渉は各単組が個別にやることになる。ナショナルセンター、産別の機能が生かされず、丸裸に等しい単組による個別交渉では、閉塞感の漂う春闘になってしまう。
春闘共闘の再構築を
労働組合員の組織率が18%台に落ちたとはいえ、1000万人を超える労働組合員が存在する。労働組合員の横断的結集を課題にする春闘にしなければいけない。組合員に「いつ春闘が始まったの」「いつ春闘が終わったの」という思いを持たせてはいけない。
連合、全労連、全労協は、11春闘を非正規雇用労働者の待遇改善と賃金の最低保障を求める方針を重点課題にしている。春闘が春闘として成果を上げるためには、職場からの学習・交流・集会の取組みから再構築しなければならない。その課題の先には、労働組合の横断的結集である春闘共闘の再構築が求められている。
|
|
|
|
|
|

