|
|
|
| 2011年2月15日 |
|
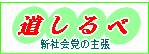 |
|
|
|
| 統一自治体選勝利へ |
|
|
| 全党の力を結集しよう |
|
|
|
|
|
|
民主党がマニフェストを投げ捨て、構造改革路線を鮮明にしつつあるなか、統一自治体選が迫っている。政治への期待感がしぼむ今日、平和と人権を真正面に掲げ、身近な自治体から運動を積み上げなくてはならない。新社会党の頑張りが問われている。
それにしても、民主党の混迷と政策転換は著しい。しかし、それを批判しても始まらない。もともと選挙互助会であり、第二保守党の地金が出ただけだ。
今日の事態を想定し、15年前に立ち上がった新社会党の運動こそが問われなければならない。正しい方針も、それが受け入れられて初めて力を発揮する。
国会議員がいないことによる、知名度の低さを嘆いてはならない。逆ピラミッドといわれた旧社会党の轍を踏まない気構えで、結党したのではないか。
自治体の変革こそ
かつて、旧社会党が国会で3分の1議席を占めた時ですら、自治体議会は、保守系が圧倒的に多数であった。民衆の生活に一番近い政治、自治体議会を変えなければ、民主主義は砂上の楼閣である。
誰かに頼るのではなく、一人ひとりが運動に関わり、政治体験を積み重ねることこそが必要である。
その大きなチャンスが、すでに前哨戦渦中にある統一自治体選挙である。現在、新社会党は全国で60名余が公認・推せんでこの選挙に挑む。新人は現在16名である。平成の大合併の影響で減少したとはいえ、自治体の政治闘争としては最大の山場である。
他方、自治体政策と国政は一心同体とも言える。廃止が問われている後期高齢者医療制度や障害者自立支援法、来年4月からの介護保険第5期事業計画、国民健康保険の都道府県単位の広域化問題も迫っている。
さらに保育行政の幼保一体化や契約制度への移行も、追いかけてきている。再び、能力主義と競争が教育行政の基調に復活している。生活保護や就職相談増大の背景には、雇用破壊が横たわっている。TPP問題も降って湧いてきた。
そしてこれらの財源はというと、税と社会保障の一体改革で、貧しい者同士で支えあう消費税増税と、国民総背番号制といえる共通番号制導入がもくろまれている。
闘いの伝統と展望
マッカーサーの憲法草案になかった憲法25条第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」を提案し、憲法に書き込ませたのは、当時の日本社会党だ。新社会党はその正当な継承者である。
もちろん、憲法前文と第9条で、支配層に頭を垂れず非武装中立を追求するとともに、雇用破壊の起点ととらえて国鉄闘争を闘い続けたわが党である。
今回の自治体選挙は、政策的に「攻め」の選挙ができる。しかし、財界はそれを見越して大阪府や名古屋市のように、ポピュリズムによって究極の構造改革・道州制への布石を打っている。
社会的な富の再配分を再構築して、貧困と格差社会を改めようとする新社会党にとって、情勢は決して甘くない。それをはね返すには、全党が一丸となって闘うとともに、身近な仲間に闘いの輪を広げることである。
|
|
|
|
|
|

