|
|
|
| 2011年4月19日 |
|
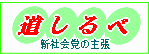 |
|
|
|
| 震災下の統一自治体選 |
|
|
| 後半戦も総力を挙げよう |
|
|
|
|
|
|
東日本大震災下の統一自治体選挙の前半戦は、民主後退、自民停滞、地域新党の躍進、護憲派の退潮という結果に終わった。
新社会党は現職を中心に踏ん張り、党籍を持つ議員は1増となった。後半戦は24日投票で闘われる。引き続き総力を挙げよう。
前半戦(都道府県・政令市の首長・議員選挙)の最大の特徴は、東日本大震災下の選挙戦だったこと。投票率はほぼ戦後最低だった。余りにも悲惨な被災地の現実、今なお進行中の福島原発事故・放射能災害は、「選挙どころか」という気持となって現れたのだろう。
「大震災の過去・現在・未来」を政治のあり方として検証し、考える時間的な余裕もなかったし、「糾弾より救援」「国難の時、国民の総団結で被災者を支えよう」というキャンペーンは、対立点をぼかしその傾向を増幅させたのである。
政治不信の増大続く
第二の特徴は、都道府県議会や政令市の選挙は、全国政党の存在感が問われるとされるが、既成政党の後退、そして大阪維新の会などの地域新党やみんなの党の躍進は、10年参院選で示された政治不信の増大が続いていることを示している。
沖縄県民を裏切り、選挙公約を見直し、第二自民党と化した民主党への失望は当然としても、自民党も基盤を減退させている。新社会党は踏ん張ったとはいえ、政治批判の受け皿となるべき共産党や社民党など護憲派総体の退潮も明らかだ。
二大政党制の下で全体として政治基盤、民主主義の融解が地域段階で進み、根拠なき新しいもの、強いものを求める危険な風潮が広がっている。大震災で多くの人が生活・労働の基盤を奪われ、人間の尊厳が問われる事態となっている。今、憲法を生かし貫く民主主義が問われているとき、私たちの闘いもまた問われている。
格差が表れ、広がる
地震、津波そして台風など自然の脅威は、人々を平等に襲う。だが災害は、その社会の断面を露わにし、弱点を暴きだす。最大の特徴は、強いものと弱いものとの格差である。
持てるものと持てないもの、金持ちと貧乏人、大企業と中小企業や農漁民、雇うものと雇われるものには格段に違いがある。また老若男女、病気や障害を持つ人・持たない人、自然災害の結果は人それぞれ現れ方が違う。そして弱いものに典型的に集中する。
さらに救援、復旧・復興の過程は、その傾向を増幅させる。それは被災者生活再建よりも、神戸空港をはじめとする大企業優先の都市計画を強引に進めた阪神・淡路大震災の経験が如実に示す。
「東日本」と「阪神」の違いは、はるかに大規模・広域というだけでなく、「阪神」は新自由主義(弱肉強食の競争)の始まりだったが、「東日本」はその結果であり、原発震災といわれるように複合的で、より深刻だ。
そして、強いものは世界的競争に生き抜くために、大震災を利用して「阪神」以上に日本列島総合理化を目論む。「阪神」では「人間の国」を目指す闘いがあり、生活再建支援法が生まれた。「東日本」は反・新自由主義の「世直し」を求めている。自治体選挙後半戦に全力を挙げよう。
|
|
|
|
|
|

