|
|
|
| 2011年8月9日 |
|
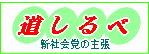 |
|
|
|
| 新執行部がスタート |
|
|
| 党員一人ひとりが運動つくり |
|
|
|
|
|
|
新社会党は初の「公選」で選出された松枝佳宏委員長に、富山栄子新副委員長を加え、長南博邦新書記長で新たなスタートを切った。自らの足元から運動をつくり、民衆の支持拡大を果たせるか否か、新社会党も民衆の政治変革も正念場を迎えている。
96年の党結成以来、中央の三役には国会議員なり、経験者がいて、その知略と人脈で運動をリードしてきた。しかし、国政選挙に挑戦しながらも国会議員不在の党となって14年、一人ひとりの党員が自ら運動を起こす必要性が叫ばれてきた。第16回大会で選出された新体制は、文字通りそれ以外に運動の前進はないことを確認することになった。
正体見せた「国家」
今回の東日本大震災と福島第一原発大事故は、国の正体をさらけ出すこととなった。途中で地震の大きさを表すマグニチュードの基準を変えて想定外の大災害との印象を与える一方、事故を過小に見せかけ、水や食料、そして学校での被曝量の基準を次々と上げた。
あらゆる分野にわたる原発利権は、金の卵を産む東京電力を温存しようと、「原子力賠償機構法」という、株主と金融機関を救済し、その負担分を電気料金値上げと増税で「国民負担」に転嫁させる仕組みをつくった。
大震災からほぼ5カ月たつ今日、いかにこの国が人の命と健康を軽視し、一部の経済的利権維持に執着するのかを浮き彫りにした。
市場経済至上主義が労働者の生活の基盤となる雇用の劣化、失業と非正規労働者の増大を招いた。社会的セーフティネットがないに等しい日本社会で、失業即ホームレス、生活保護という、格差と貧困問題を露にした。
しかし、それらを解決すると期待された政権交代はあっけなく期待を裏切ることになった。そのため政治不信は限りなく強まり、小選挙区制によってもたらされた二大政党制は機能不全に陥り、政治へのまともな期待は終わったといっても過言ではない。
その間隙を突いて統一自治体選挙では、橋下徹知事が率いる大阪維新の会やみんなの党が躍進した。大阪府議会で多数を手にした維新の会は、間髪を入れず1人区が全体の8割となる議員定数削減を問答無用で強行した。これによって府知事とその与党はフリーハンドを得ることになった。かつてのナチスを髣髴とさせる所業だ。
危機の時に見る好機
私たち新社会党は、このような時代をどう変えるのかが突きつけられている。この認識を労働者・民衆の党として、広く党内外で共有できるのか、そして共に闘えるのかということである。
少なくとも党員は、一人ひとりがそれぞれの持ち場で一目置かれる存在であるために、その時々の課題を率先して学習し、それを広めることによって運動化する責任を負っている。もちろん一人でやれることには限界がある。だからこそ党内外で交流を深め、叱咤激励しながら進もう。
憲法の実現のために
66回目の敗戦記念日を迎える今、国内外の数千万人の犠牲を経て手にした不戦と民主主義と人権の憲法を真に実現する機としたい。その転機は、自らつくりださねばならない。
|
|
|
|
|
|

