|
|
|
| 2011年8月16日 |
|
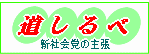 |
|
|
|
| 11年度の最賃引き上げ |
|
|
| 38府県でわずか〝1円〟 |
|
|
|
|
|
|
労働者の賃金の下支えをする今年の地域別最低賃金の引き上げについて、全国加重平均で6円引き上げる目安額が決まった。引き上げといっても、38府県はわずか1円の引き上げであり、年収120~130万円でどのように生活しろというのだろうか。
全国平均わずか6円
2011年度の最低賃金引き上げは、全国平均でたった6円となった。昨年度は17円の引上げで全国平均730円だった。そして、20年までのできるだけ早い時期に全国平均800円を確保し、景気回復に配慮しつつ全国平均1000円をめざすと合意していた。
しかし、震災を理由に合意事項を反古にするばかりか、被災地域だけではなく38府県でわずか1円の引上げにしかならなかった。復興の主役は企業、「経営あっての雇用」という使用者側の論理が、労働者の生活再建を奪う形となった。
平均6円の引上げの中身は、被災地3県を含む38府県で1円の引上げにすぎず、10円以上の引上げとなるのは、北海道13円、東京16円、神奈川18円の3県のみ。その結果、当面の目標の800円以上は東京の837円、神奈川の836円の2県でしかない。
そんな、東京、神奈川など9都府県は、これまで最低賃金が生活保護を下回る逆転現象になっている。今年度の引上げで東京、京都、広島で逆転現象が解消されることになる。しかし、改正最低賃金法施行4年目にいたっても依然として北海道、宮城、埼玉、神奈川、大阪、兵庫が生活保護を下回る水準だ。
その一方で、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の5県は引上げ後も643円と全国平均を大きく下回るが、生活保護以下ではない。
貧困化は大都市部に顕在しており、日本の労働者の賃金は低すぎる。国税庁の調べでも年収200万円以下の給与所得者は、1100万人と全体の四分の一を占めている。
「働く貧困層」の解消こそ、経済・社会発展のキーポイントだ。時給800円でも、年収は150万円~160万円しかならない。これ以上生活を切り詰め、ガマンすることはできない現状にある。
経営者がいつまでも利益にしがみつき、「いかに税金は払わずにすませるか、いかに労働コストを下げることができるか」など追求している限り、社会の発展も途絶える。
産別最賃とリンク
産別企業の初任給引上げは、賃金底上げの大切な部分になるが、それにリンクするのが産別最低賃金の引上げだ。私鉄総連は今年の産別最低賃金を、地域最低賃金の月額換算額を下回る地域については13万800円(月額換算額=2011年度地域別最低賃金額×173・8時間)とした。時間給にすると752円にすぎない。
地域最低賃金が月額換算額を超えた地域は東京と神奈川で、東京は14万2690円、神奈川は14万2168円になる。13万800円を超えるのは、この2都県しかない。
地域最低賃金を上げることは、産別最低賃金を押し上げることになる。だからこそ、労働者の団結をつくらなけらばならないし、産別闘争を強化することなしに賃上げは勝ち取れないのである。
|
|
|
|
|
|

