|
|
|
| 2011年10月11日 |
|
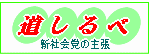 |
|
|
|
| 南スーダンPKO |
|
|
| 「人道」掲げ利権と派兵を追求 |
|
|
|
|
|
|
野田内閣は、南スーダンPKOへの陸自部隊派遣に本腰を入れ始めた。「復興・人道支援」を掲げるが、本音は石油資源の獲得をめぐり、中国などに対抗する思惑が強い。併せてこうした「実績」の上に、海外での武力行使の条件を拡大する狙いもある。
20年以上のスーダン内戦を経て今年7月、南スーダンが分離独立し、アフリカで54番目の国、国連で193番目の加盟国となった。
スーダンは、19世紀の英国(南部)とエジプト(北部)による植民地支配、第二次大戦後の南北統合を経て56年に独立。だが北部のアラブ系政権は連邦制の約束を破り、アラビア語を公用語として非アラブ系中心の南部を支配。対して南部でスーダン人民解放軍(SPLA)が反乱、内戦が続いた(〜72年)。
次いで北部では、軍事政権が南部の石油資源を支配し、83年にイスラーム法を導入、第2次内戦(83〜05年)となった。犠牲者は約190万人、難民・避難民は400万人以上にのぼった。スーダン西部のダルフール地方でも、アラブ系による大規模な虐殺と無数の避難民の悲惨な状態が続き、国際的な救援が行われてきた。
米中の角逐の場に
米国は93年、スーダンをテロ支援国家に指定し、経済制裁。ところが世界中で資源・エネルギーを求める中国が進出し、石油生産の大半を獲得した。
これを見た米国は、巨額の経済援助を投じて南北和平と南部の分離独立をスーダン政府に認めさせたが、それに対応して中国も、南部の勢力に急接近。
7月9日の南スーダン独立は、この文脈では「米外交の勝利」とされるが、長年の収奪と内戦で荒廃、疲弊した国土の復興と国民の生活再建には途方もない努力が必要になる。
南スーダンの再建の最大の原資は石油。大国側からは、その利権をどの国が獲得するかが問題で、今回の南スーダンPKOにも、その思惑が絡んでいる。
このPKOが安保理で決められたのは独立の前日。軍事要員7千人と警察官など文民900人で構成される。
自衛隊派兵が主眼
国連の藩基文事務総長は8月、日本に陸自施設部隊の派遣を求めたが、北澤防衛相(当時)は、「当面、司令部要員派遣の派遣」にとどまっていた。だが野田内閣になると、対米協調と「日の丸外交」の外務省の主導で「震災支援への返礼としての国際貢献」などを理由に、施設部隊300人の派遣検討に踏み込み、9月24日に現地調査団を出発させた。
背景には、事務総長が中韓両国にも施設部隊派遣を求めており、決定が遅れれば「治安が比較的安定しアピール度が高い」首都ジュバでの活動を奪われるとの判断や、その実績を同国の石油資源獲得で売り込む狙いも。
現地では、医療、教育、法制整備など文民による民生支援の必要は途方もなく多いが、政府はあくまで自衛隊派兵が最優先事項だ。
民主党の前原氏は9月7日、「PKOで自衛隊とともに行動する他国軍隊を守るため武力行使できるようにすべきだ」と米国で講演し「次」をアピール。 南スーダンPKOへの自衛隊派兵は、利権と軍事の思惑にまみれている。
|
|
|
|
|
|

