|
|
|
| 2011年11月22日 |
|
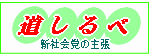 |
|
|
|
| 共通番号制 |
|
|
| 「弱者に給付」はまやかしだ |
|
|
|
|
|
|
民主党政権は、税と社会保障の一元的な管理のため全ての国民に番号を付ける「共通番号制」の導入への作業を進めており、開会中の臨時国会に関連法案を提出し、成立させる方針だ。国民を番号で管理する国家・国民総背番号制に改めて反対を表明する。
消費税増税と裏腹で
野田佳彦首相は、今月初め仏カンヌで開かれたサミットで「消費税率を2010年代半ばまでに10%に引き上げる」と表明し、国際公約した。来年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。また、先日ハワイで開かれたAPECでTPP交渉への参加を表明した。
消費税、TPPといった国論を二分する問題を外圧で突破・強行しようとする野田首相の姿勢・手法は国民をないがしろにしたものであり、許されない。
その消費税率倍増と裏腹にあるのが、「社会保障・税に関わる共通番号制度」導入で、「マイナンバー」という名称を付けている。政府は14年6月の番号配布、15年1月の運用開始を掲げている。
政府・与党が6月に決定した「社会保障・税番号大綱」は、共通番号制度を採用することによって、「低所得で資産も乏しいなど、真に手を差し伸べるべき者に対して給付を充実させるなど、社会保障をよりきめ細かに、かつ的確に行うことができる」としている。
だが、この「理念」と「マイナンバー」などという名称がまやかしであることは、11年度の社会保障予算が自公政権が強行した新自由主義・社会保障削減路線を基本的に修正することなく、国民生活に関わる補助金・負担金を大幅に削減したことで明白だ。
共通番号の「神話」
「大綱」は副題で、「主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築」をうたい、「住民基本台帳ネットワークに係る最高裁判決の趣旨を十分踏まえる必要がある」とする。だが、主権者たる国民に憲法13条が保障する自己情報コントロール権、すなわちプライバシー権を真っ向から否定したのが、「住基ネット」ではないのか。
全国で取り組まれた住基ネット裁判は、地裁・高裁合わせて34の裁判で2つの違憲判決を勝ち取り、請求が棄却されたいくつかの判決でも画期的な内容を勝ち取った。その最大の成果は、国家がデータマッチング(検索・名寄せ)によって、国民一人ひとりを丸裸にする危険性を明らかにしたことである。
住基ネットが行政機関だけが情報を取り扱う仕組みであるのに対し、共通番号制度は金融や医療機関など民間の利用を前提としており、プライバシーの侵害は住基ネットの比ではない。共通番号制度は、国家による個人情報の一元管理システムの完成なのである。
住基ネット裁判で政府は、データマッチングの危険を否定し、最高裁は08年3月6日の判決で政府の主張をオウム返しする論理によって、住基ネットに対する国民の疑問・不安を封鎖した。
国が安全だというものが本当は安全ではなく、危険極まりなく、大変な災禍を国民にもたらすものであることは、福島原発事故で明らかになった。原発神話に騙された轍を、共通番号制度バラ色神話で踏んではならない。
|
|
|
|
|
|

