|
|
|
| 2011年12月27日 |
|
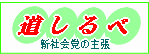 |
|
|
|
| 今年を振り返る |
|
|
| 世界と日本は新たな危機に |
|
|
|
|
|
|
毎年恒例の1年回顧の時期になった。近年は、毎年「かつてない」とか「未曾有の」という表現が繰りかえされた。今年はそれが形容詞ではなくなり、世界の変容と原発が、私たちの暮らしや安全を脅かす切迫感を持つに至った。歴史は岐路に立っている。
機能不全状態の政治
物事は単純には繰り返さない。繰り返しはいつかは質的に新たな段階に入る。この1年は、世界と日本が新たな段階にさしかかる徴候を示した。
第一に、EUの財政危機に端を発した金融危機である。2008年秋のリーマン・ショックを想起し、世界は震撼している。だが今次金融危機の兆しは、金融危機対策自体が生み出したこと、BRICSに波及していることなど、一段と深刻度が深まり、3年前と同じ繰り返しはできなくなっている。
第二に、政治の「機能不全」である。自民党中心の政治が大きく揺らいだ1990年代半ばのように錯覚する。
激動する情勢に旧来の政治システムでは対応できないから、小選挙区制で政権交代可能な「二大政党制」をめざすと言われた。だが今、民主党政権は3人も看板が代わった。
民衆の暮らしも、大震災も、原発事故も、事態は90年代より一段と切迫しているのに、違いの分からない「二大政党」の駆け引きばかりの国会では、何も決まらない。メディアではまた、一院制論や選挙制度改革論議が再燃している。
想定した危険の噴出
第三に、「二大政党」不信は議会不信とも重なり、自治体レベルで噴出し始めた。2月の名古屋市長選と愛知県知事選で、議員定数半減を掲げた「河村旋風」が吹いた。その勢いはやや停滞したかに見えたが、大阪の「橋下旋風」は、国政への影響など新たな展開を見せている。
同じく政治不信の高まった90年代には、これだけあからさまな「独裁」で人気を博す政治潮流はなかった。
第四に、原発事故だ。従来も事故が続発していたが、大震災という契機によって一気に想定された危険のすべてが噴出した。
一方、わたしたちにとって唯一歓迎すべき変化も生まれた。9月19日の東京での「6万人大集会」に象徴される脱原発運動の前進だ。チェルノブイリ原発事故後に高揚した脱原発運動が短命だったのに比べ、質の違う前進を見せている。
危機を打開する主体
だが、脱原発を唱える政党が世論調査では低迷し、橋下支持を公言する諸党派が原発批判票をも取り込みかねない。人間らしく安全に生きる権利の危機に直面しながら、民衆の声を代表し、事態を打開する主体が危機にあることが、最大の問題なのである。
メディアも「市場が民主主義を否定する」と指摘する。新自由主義による資本のグローバルな搾取と収奪競争は、民衆の切実な期待に実際に応える対抗勢力が形成されない限り、「自由」の反対物に転化しかねない。
ファシズムと呼ぶかどうかは別として、民主主義の危険水域は間違いなく近づいている。新社会党が一貫して訴えてきた護憲派の共同が、待ったなしの段階に入った。
|
|
|
|
|
|

