|
|
|
| 2011年6月28日 |
|
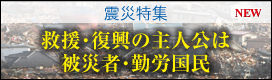 |
|
|
|
|
|
|
3・11大震災 生活再建の視点(下)
自治体の機能回復が急務 被災者をまず雇え
新社会党神戸市議 粟原 富夫
|
|
|
|
|
復興は、被災者の生活再建が最優先だ。それには、市町村の要求を県や国がきちっと受け止めることが必要だが、阪神・淡路大震災後、「平成の大合併」があった。広域行政・道州制志向のなかで自治機能が崩壊、もしくは非常に低下した。
行政の機能が壊滅的な打撃
そうした地域では、災害状況や孤立集落の把握、救援物資の配布にも困難をきたした。さらに東電福島第一原発災害では、原発を誘致し、電源立地交付金などに依存してきた原発立地自治体で、大量の放射能漏れ・汚染によって強制退去という最悪の事態に陥っている。
また、広域行政・行政の集約と同じ文脈に、宮城県が提起した漁港の集約化・企業化がある。漁民は反対しているが、漁民の思いに反することを行政が押しつけている。これで生活再建最優先の復旧・復興はできるのか、疑念を持つ。
住民・被災者の置かれたそれぞれの状況を尊重した対応をするには、広域行政では無理だ。住民自治を基本にした機能が求められるが、合併で壊されている。
その上に、今回の震災では三陸海岸地域をはじめ原発災害の被災地域で、市役所や役場が人的にも建物など物理的な面でも大きな被害を受け、行政の機能そのものが壊滅的な打撃を受けた。
生活再建を軸とした復旧・復興のためには、自治体職員の確保、増員が急務だ。被災者の生活再建を進める上からも、自治体が被災者を期間雇用することなども積極的に行うべきではないか。
さらに国や全国の自治体からの専門職員、一般職員の長期派遣による支援態勢の確立・強化が求められている。しかし、「三位一体改革」と自治体合併によって、派遣する側の自治体でも、人手不足と超過勤務が恒常化して被災地に職員を派遣する余力・ゆとりがなくなっているの現状だ。
「公務員を削減して効率的な行政に」という流れを根本的に変えなくては、被災者一人一人の生活再建を図る方向は見えてこない。自身も被災者でありながら避難所で中心になって頑張っているのは自治体労働者であり、学校の先生たちだ。
災害救助隊に今こそ改編し
自衛隊の活動ばかりスポットが当っているが、被災地の自治体職員、全国の自治体から派遣されている労働者の献身的な活動がもっと取り上げられていいのではないか。
自衛隊の活動で言えば、東日本大震災では10万人体制で救助・復旧に00両、航空機は7000機、人命救助は165人、遺体収容が1221体。自衛隊は、人命救助にはそれほど大きな役割は果たさなかった。
人命救助は圧倒的に地域の人々の助け合いや警察、消防だった。いざ地震となったときに力を発揮するのは地域コミュニティだ。
阪神淡路の時、神戸のポートアイランドに自衛隊が水を運んできた。装甲車が引っ張っていたのは、わずか1トンの水が入ったタンクで、多くの被災者が必要とする水の量ではなかった。
つまり、自衛隊は戦争をするための組織で、人を救助・救援するための組織・装備にはなっていない。阪神淡路でも東日本でも明らかになったことは、自衛隊を災害救助隊に改編すること、それこそ災害大国日本では求められていることだ。
災害救助隊なら、世界の被災地にも直ちに派遣できるし、大きな国際貢献ができる。憲法の理念そのままに「国際社会にいて名誉ある地位を占める」ことができる。
|
|
|
|
|
|

