|
|
|
| 2011年7月19日 |
|
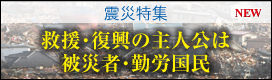 |
|
|
|
| 大震災・復興をめぐる争点 |
今こそ憲法25条・13条の完全実施を
全国自治体労働運動研究会 上野 義昭
|
|
|
|
|
過去の震災に比べても遅い、東日本大震災の復旧・復興。政争・私益がからみ、新自由主義構造改革への復帰を狙う動きも増大している。復興は、格差を生み出しながら進められる。誰の視点で語られた、誰のための復興か、を見極める必要がある。
資本にとっての震災
 |
マイナスからの出発を強いられる地震・津波に被災した
建物(岩手県大槌市) |
個々の資本が大きなダメージを受けても、資本一般にとっては震災はマイナスばかりではない。便乗切りは論外としても、古い資本を強制的に廃棄することにより、過剰設備は解消され、新規投資やイノベーションを促す。復興需要は、被災していない資本に新たな市場を提供し、遊休設備を稼動させる。
一時的な停滞の後、往々にして成長をもたらす。この間投資に回らず、内部留保を増やしてきただけの企業の巨大な余剰マネーの出番となる。
だが今回は、困難が大きいのも事実。ツナミ、フクシマ、グローバル化によるものだ。全てが根こそぎ流されて、九〇年代半ばから東北地方に集積していた、先端的な部品のサプライチェーンの分断により、国内外のグローバル生産がストップした。政府与党の新成長戦略も頓挫した。
原発輸出や観光立国は当てが外れ、TPP参加も遅れた。日本離れが、風評被害と多国籍企業の海外逃避の二面で進む可能性も高まった。エネルギー供給のボトルネックは、経済成長の足を引っ張るとの懸念も広く存在する。
新自由主義は災害を歓迎する
 |
| 今なお収束のメドさえたたない東電福島第一原発 |
「災害資本主義」という主張がある。人々をパニックに陥らせ、変革を拒む人々の抵抗の意思を崩し、新自由主義的な秩序を唯一の秩序として受け入れさせる、というものだ。確かに、新自由主義構造改革はどこでも、人々に考える暇を与えない強引なリーダーシップによって行われてきた。加えて、災害はショック療法となるだけでなくビジネスチャンスでもある。
ところが、菅政権のスピード感の欠如はまさにこれらと真逆であり、せっかくの機会を逸したことで財界を失望させた。しかし、新自由主義への復帰は資本の不動の基本戦略だ。すでに3・11以前から財源問題がその突破口となるべく浮上していたが、復興論議はそれを加速する。
マニフェスト見直しと称して政権交代効果をリセット、財源確保論議の出口は、税・社会保障一体改革など構造改革の再始動と、「安定財源」確保という名の消費税増税だ。不人気の道州制も再登場させる。
現時点では、経済同友会の提言が資本のホンネをもっともよく表しているだろう。漁業や農業の復興論議で焦点になっているのが「特区」も使った規制緩和だ。規模も資力も小さい、地元漁民・農民が復興の主体となるのは無理と、大企業への市場開放、選択と集中を迫る。現在、自衛隊出身の村井宮城県知事が、大企業とともに準備を進め、その先頭に立っている。
改憲策動も再始動
災害にあたっては「強い手」を求める声が高まる。非常事態における軍隊という暴力装置とこれを動かす権力、国家意思の迅速な決定・執行、復興計画における私権の制限……これらを改憲論議と結びつけようとする。 「民主党憲法調査会」の再開や、改憲手続緩和を目的とする「憲法九六条改正を目指す議員連盟」の立上げが続いている。
しかし、憲法というのなら、被災者に保障されていない25条(生存権)や13条(個人の尊厳)の完全実施こそ必要だ。阪神淡路大震災以降、住宅再建への公費支援は違憲という論難をはね返し、生活再建支援の範囲は住宅再建支援にまで拡大してきた。大企業の支援で傘下の下請企業は救われる。資産格差が復興格差となる。この現状を変えていく取組みから、現代的攻勢的な護憲闘争の推進が求められる。
日本社会の大転換へ
3・11は、人びとの意識を大規模に変える契機となった。過酷な経験は、広範な脱原発のうねりをグローバルに実現した。原発停止の具体化に着手する段階に進んだのだ。これに必死に抗するのが電力危機論による原発の必要性の強調だ。
しかし、企業の自家発電や、原発以外の発電所の稼働率引き上げ、高い効率の発電施設の新規発注など原発ぬきで現実的解決は進んでいる。
他方で、私たちは電気を野放図に使う生活を拒否するときだ。3・11は、大量消費・大量廃棄の米国型浪費資本主義のライフスタイルを転換する契機となりうる。震災後高まった支えあいの気運。これに乗じた、「オールジャパン」への国民統合へ動員しようという企みは、本来的に無理を通そうというものだ。新自由主義に対抗する共同性の構築を対置することこそが自然なのだ。
|
|
|
|
|
|

