|
|
|
| 2011年9月20日 |
|
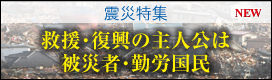 |
|
|
|
| 原発政策をめぐる 社会党と共産党 <上> |
「平和利用は拒否しない」
|
|
|
|
|
社会党は、左右合同によって魂を失い90年代の解党の遠因を作ったが、合同直後(55年末)に松前重義氏らに引かれて原子力基本法に賛成したという禍根を残す。これらのことに関して、『赤旗』は8月12日から連載して批判を展開したが、看過できない内容なのでここに反批判したい。
■□
 |
浜岡原発を廃炉にと訴えてデモする市民たち
=7月16日、静岡市内で |
共産党がこの法案に反対したからといって、原発問題に正しい方針をもって大きな組織を活かし、原発建設を阻止しえたわけではない。共産党は3月11日の福島事故によって方針を変えるまでは、条件を付けながらも、原発の建設や稼働に反対ではなかった。
03年6月の綱領制定時にも不破哲三議長は次のように強調している。「将来展望にかんしては、核エネルギーの平和利用をいっさい拒否するという立場をとったことは、一度もないのです」「原発の段階的撤退などの政策を提起していますが、それは、核エネルギーの平和利用の技術が、現在たいへん不完全な段階にあることを前提にしての、問題点の指摘であり、政策提起であります。」
上田耕一郎氏がとりまとめた『日本経済への提言』(77年)では、「厳しい規制を加える」ことを前提にしながらも、稼働中、建設中の原発は稼働続行、建設続行・計画通りの完成を想定して「エネルギー供給見通し」に算入している。そこでは「燃料や技術の面で完全に対米従属になっており、自主的立場がきわめて弱い」ことこそが悪いという。
では日本独占資本が、オーストラリア等からウランを自主的に購入して濃縮したり、主従転倒して米ウェスチング・ハウス社を買収したり、仏アレバ社と提携してやるのなら、原発も大いに結構となりはしないか。「大企業の利益を抑え、安全性を重視した長期的な展望に立つ総合的な研究・開発体制」をもつべき、という条件を付けてはいるが。
■□
これでは同党が低レベル放射性廃棄物を海洋投棄するための法整備(原子炉等規正法改正) (80年)に賛成してしまったのも無理はない。原発稼働を認め、エネルギー供給の任務を与えるからには、廃棄物をどうするかの方策も欠かせないからだ。(幸いドラム缶等の海洋投棄は国際的な反対の盛り上がりで、できないことになったが)。
かつて原水禁の「いかなる核にも反対」は誤りで「ソ連の核はよい」として、分裂組織を作る一因となったことも想起される。誤りはいつも他の党で、共産党は一貫して正しかったとする態度は改めた方がよい。誤りは認め、方針を正すことを明らかにする方が信頼される。それは「転向」ではなく「進歩」になるのだから。(原野人)
|
|
|
|
|
|

