|
|
|
| 2011年9月27日 |
|
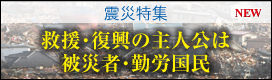 |
|
|
|
| 原発政策をめぐる 社会党と共産党 <中> |
「中期エネルギー政策」
|
|
|
|
|
 |
どの党も、平和利用なら条件付きでよいではないかとしていた中で、社会党は72年1月の第35回党大会で、関係19県の共同提案として、『原子力発電所、再処理工場の建設反対運動を推進するための決議』を採択した。
これがテコとなって、党と県評、地区労、住民組織、原水禁国民会議が中心となった原発反対闘争は各地で発展を遂げることとなる。党内には自治体議員を中心に「原発対策全国連絡協議会」(原対協)
(初代会長・栗原透高知県議)が組織された。
建設に反対する闘いは、完成してからの稼働にもさまざまな形で反対する運動に継承され発展した。稼働を認めることは高レベル廃棄物の処理・処分や大事故発生にもかかわるからである。
■□
反対運動が大きくなるにつれて、これを切り崩そうという介入も、様々な形で大きくなった。85年1月の第49回党大会には、外注(平和経済国民会議)で起草された『中期社会経済政策案〈総論〉』がかけられた。そのなかのエネルギー政策に関する核心は、まずは稼働中の原発と建設中の原発を容認させようとすることにあった。
これに対して原対協をはじめ、多くの仲間が反撃に立ち上がり、大会のなかで大きな修正を勝ち取った。チェルノブイリ事故に1年先立つ闘いだった。
修正された政策〈総論〉に基づいて作られた『中期エネルギー政策』では、今日でも生きている視点が整理され、稼働も認めない脱原発の政策が明確にされている。
その中では「われわれの長期エネルギー需給見通し」でも、「電源構成計画」においても、「建設されてしまった原発については(休止設備)としてカッコの中におさめ、他の部門により需要の100%をまかなえる計画」として、それを容易に実現できる政策を提案している。
■□
残念ながら総評が解体され、御用組合からの介入も大きくなって、党内民主主義が形骸化していった。山花貞夫委員長らが小選挙区制を呑んで細川内閣に入閣し、村山富市委員長が自民党に担がれて首相になり、社会党の基本政策を転換するという致命的な誤りを犯すこととなった。
多くの国会議員が民主党に行き、社会党は崩壊して、96年には安保・自衛隊・原発を容認する基本政策をもった社民党が生まれた。
それとともに、本来の基本政策を堅持する闘いの先頭に立っていた平和戦略研の矢田部理、山口哲夫・両参院議員の旗の下に、小森龍邦、岡崎宏美・両衆院議員、栗原君子参院議員、全国の反原発・脱原発の闘いを担っていた稲村稔夫前参院議員、関晴正、吉田正雄・両前衆院議員、田辺栄作・前新潟県議、渋谷澄夫・北海道議をはじめ原対協の人たちも馳せ参じて新社会党が結成された。(原野人)
|
|
|
|
|
|

